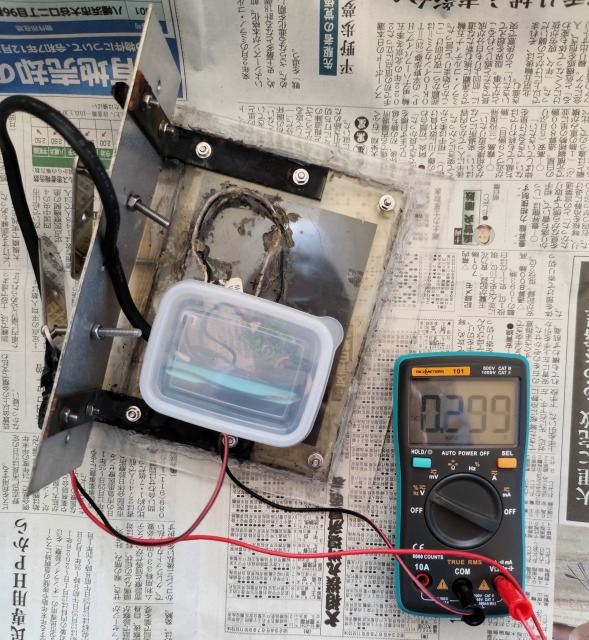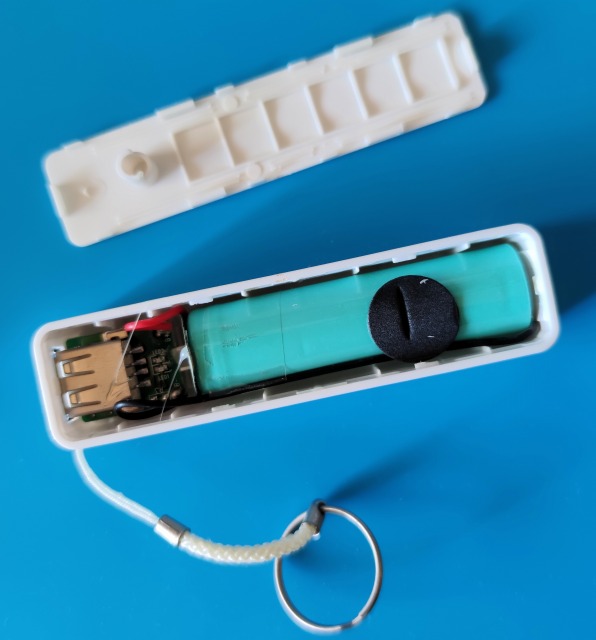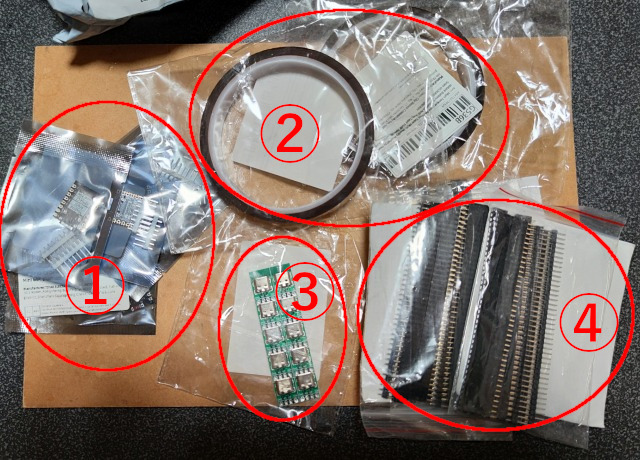NOAA用サーバをADS-B受信で利用する
先日からサーバのメンテナンスを実施
整理してWEBサーバはメールサーバを含むサーバ,NOAA受信で利用していた外部サーバを(おかしな名称なので)室外サーバに変更,室外サーバは夜間休止とした
利用しなくなった室外サーバにはRTL-SDRが接続されているので,まずはADS-B受信で利用してみる
ADS-B受信のマップ表示にはVirtualRadarを利用,公開はリバースプロキシで対応することにした
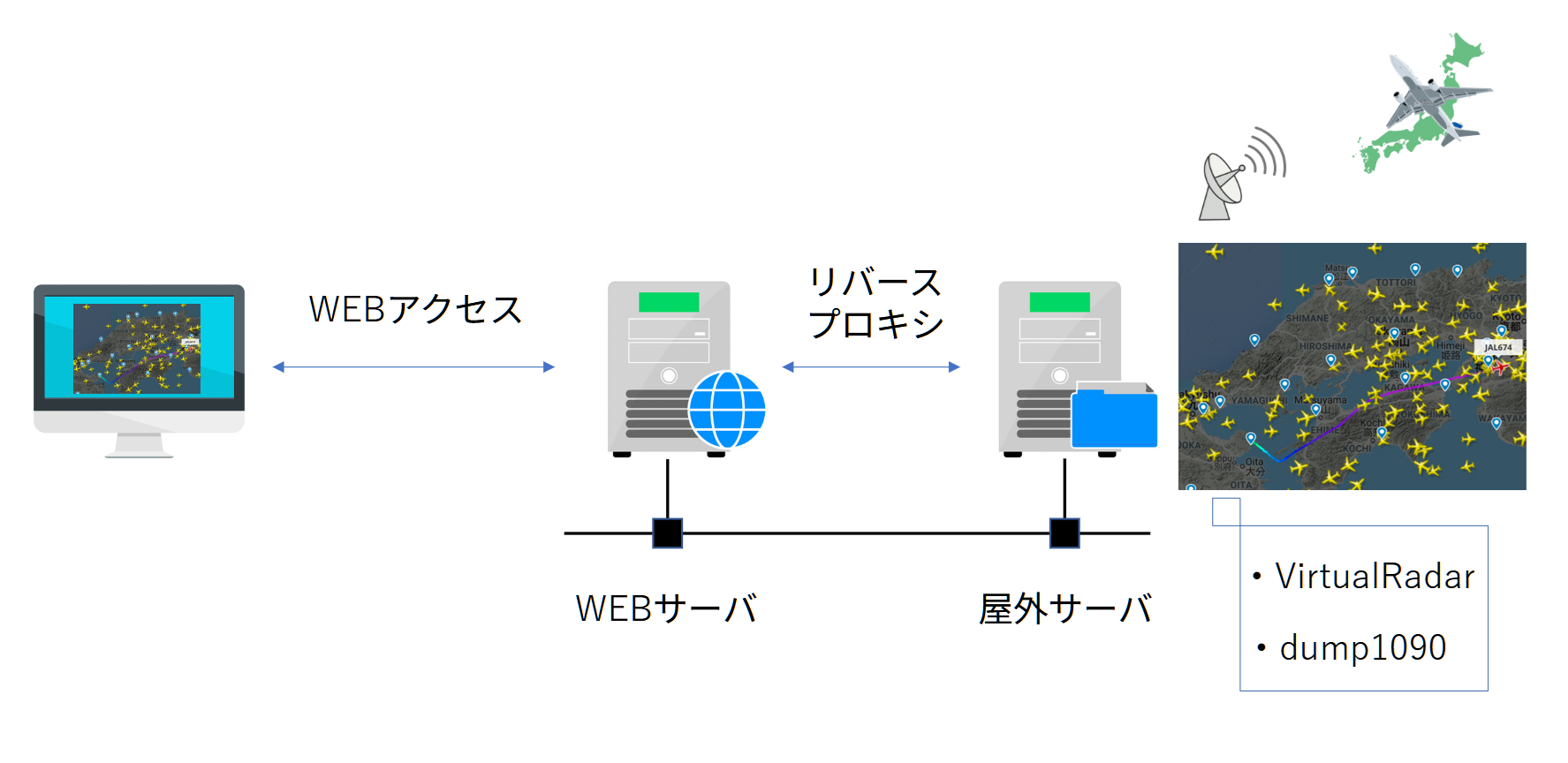
WEBサーバ
セキュリティ確保のため直接アクセスとしないでWEBサーバ経由とする
Apache2のリバースプロキシを設定
参考:https://rainbow-engine.com/apache-reverseproxy-howto/,https://rainbow-engine.com/apache-reverseproxy-https/
モジュールの有効化
a2enmod (モジュール名),a2dismod (モジュール名):モジュール名は複数指定可能
# a2enmod proxy_http
# a2enmod proxy_balancer
# a2enmod proxy
# a2enmod lbmethod_byrequests # 必要ない?
設定ファイルに追加
# vi sites-available/000-default.conf
ProxyRequests Off # リバースのみはOff,フォワードも使うならOn
ProxyPreserveHost On # 元のホスト名を保持する設定のことだが,これがあると動作しない
<Proxy *>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>
ProxyPass /vrs/ http://(サーバ)/
ProxyPassReverse /vrs/ http://(サーバ)/
最終的に「VirtualRadar」「dump1090」用に2つProxyPassを作成
注)ProxyPasのバックエンドのURL(上記では(サーバ)の部分)にドメインを付けるとポート指定が無視されるようだ(拙者の環境が悪いのかな?)
Apache2を再起動
# systemctl restart apache2
室外サーバ
アンテナは解体も簡単ではないので,しばらく接続中のNOAA用で試行して,ADS-B受信の設定が落ち着いたら変更する
Virtual Radar Serverのセットアップ
参考:https://www.virtualradarserver.co.uk/mono.aspx
Linux用といってもmonoで動作させるのでWindows版と同じ
(monoのインストール)
$ sudo apt-get install mono-complete
(VirtualRadarServerのインストール)
$ cd
$ wget http://www.virtualradarserver.co.uk/Files/VirtualRadar.tar.gz
$ wget http://www.virtualradarserver.co.uk/Files/VirtualRadar.exe.config.tar.gz
$ cd /srv
$ sudo mkdir vrs
$ cd vrs
$ sudo tar -zxvf ~/VirtualRadar.tar.gz
$ sudo tar -xvf ~/VirtualRadar.exe.config.tar.gz
最初の1回admin,password付きで起動
$ mono VirtualRadar.exe -nogui -createAdmin:admin -password:password
Local address: http://127.0.0.1:8080/VirtualRadar
Network address: http://・・・:8080/VirtualRadar
2回目以降
$ mono VirtualRadar.exe -nogui
ブラウザでアクセスして確認(画面生成のためか少し接続時間が掛かる)→ まだ受信していないので航空機は無い
システム起動時自動起動させる
(スクリプト作製)
$ cat vrs.sh
#!/bin/sh
#
mono /srv/vrs/VirtualRadar.exe -nogui
$
(vrs.shを/etc/rc.localに登録)
$ cat /etc/rc.local
/srv/lbin/vrs.sh 1>&2&
dump1090のインストール(ADS-B受信用だが,マップ表示も可能)
$ sudo apt search dump1090
ソート中... 完了
全文検索... 完了
dump1090-mutability/jammy 1.15~20180310.4a16df3+dfsg-8 arm64
ADS-B Ground Station System for RTL-SDR
$ sudo apt install dump1090-mutability
$ sudo vi /etc/default/dump1090-mutability
(特に変更の必要ないがWebサーバなしでインストールしていると以下のようにnoとなっているかも)
START_DUMP1090="no"
MAP表示(試行)
- VirtualRadar
- dump1090-mutability
参考
以下が今後追加で参考になりそう(ありがたい)
- https://ameblo.jp/icchi-rjfm/entry-12546868774.html
- https://intaa.net/archives/21187
- Apache ProxyPass設定ミスの原因と解決方法